
施工箇所は地下十数m、“直(じか)には見えない”技術で支える
酒井康太さん
地盤改良工
地盤改良工事とは、埋め立て地・湿地などの軟弱な地盤を補強して、地上に重い構造物をつくっても沈下しないようにする工事のことです。
土壌の状況や周辺環境によって様々な工法がありますが、セメントなどの固化材を地中に噴射し、周辺の土や水分と攪拌して、地盤改良する方法がよく知られています。
地盤の状態に応じて最適な固化材を配合する知識と、地中で噴射・撹拌が確実に行われていることを計器で確認しながら重機を操作する技術が求められます。
そこにできるものをイメージする
日特建設株式会社・酒井康太さんが現在従事しているのは、新潟中央環状道路の建設現場。もともと水田だった用地は強固な地盤とは言えず、立体交差のバンクなど、盛土する箇所には地盤に大きな荷重がかかるため、軟弱な部分を地盤改良している。 この現場での地盤改良は、「撹拌翼」と呼ばれるビットを改良機本体で地中深くまで貫入し、固化材を土中に噴射・撹拌して行う工法のため、施工中も施工後もその成果は目に見えない。
「まずは事前にボーリング調査で土を採取し、試験室にて数種類の固化材(主にセメント)と3種類の配合量にて試験を行い、その結果で設計強度を満たす最適な固化材の配合を決めます。この現場で採用しているDJM(ドライジェットミキシング)工法は、セメントの粉粒体を固化材として噴射しながら、地中で土と混ぜ合わせて地盤を改良します。実際に作業する現場にはもちろん構造物はまだありませんが、そこに将来何がつくられるのかを想像して、その構造物がきちんと建つためには地盤にどのくらいの強度があればいいのかを考える…そんなイメージです」
自分の目で直接確認できない地中深い部分で、改良が上手くできているかどうかの感覚はわかるのだろうか。 「軟らかい土には水分が多く含まれていて、そこに固化材の粉体が混ざることで水和反応が発生して徐々に固くなります。改良機で撹拌するときの抵抗が強くなれば、『あ、固まってきてるな』という感覚は伝わりますね」
 施工箇所を変える際に、引き抜いた撹拌翼にこびりついた土を除去。
施工箇所を変える際に、引き抜いた撹拌翼にこびりついた土を除去。プロペラのようなビットの先端から、セメントの粉を噴射する。
 セメントの粉体を配合するためのプラントも自ら操作する。
セメントの粉体を配合するためのプラントも自ら操作する。重機が大好きだった少年時代
酒井さんは、1981年、北海道札幌市生まれ。子どもの頃から建設機械が大好きな少年だった。
「自分ではよく覚えてないんですが、親が言うには、小さい時から電車とか車には見向きもせず、工事現場の重機を見かけると喜んでいたらしいです。物心ついてからも、もちろん好きで、それが高じて工業高校に行きました」
進学した地元の工業高校では、土やコンクリートの性質を学びながら自身の興味の対象を探っていった。
「測量の授業で野外に出た時も、測量そっちのけで土をいじったり、においを嗅いだり(笑)。その時はまだ地盤改良とかは知りませんでしたが、とにかく『土に関係する仕事をしたい』と思っていましたね」
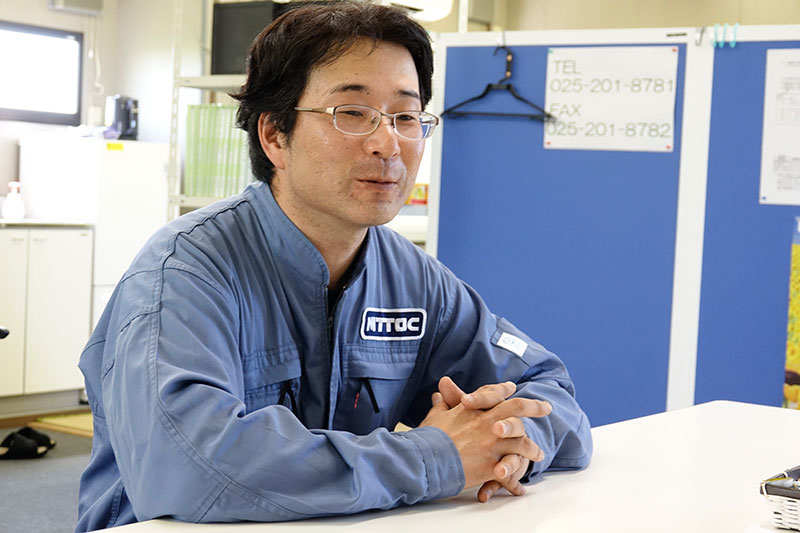 入社以来埼玉県在住だが、全国の現場を飛び回っている。
入社以来埼玉県在住だが、全国の現場を飛び回っている。「社員オペレーター」として入社
日特建設には、特殊な土木工事で豊富な実績を持つ技術系社員が多く在籍している。酒井さんは、高校卒業後に入社以来、同社で社員オペレーターとして約20年勤務している。
「男三兄弟の末っ子なので、最初から親元を離れて働きたいと考えていました。高校時代はガソリンスタンドでアルバイトをしていたんですけど、その頃から『自分1人でどこまでできるか、やってみたい』と…。まあ自分への挑戦ですかね」
入社後、同期入社5人の中で酒井さんだけ現場に出るのがたまたま遅くなったため、重機の操作や地質について必死で学んだ。
「当時はまだまだ『見て、盗んで覚えろ』の時代でした。自分でやってみて上手くいかなければ、先輩の作業の様子を観察して身につけていましたね」
 この現場で使用している重機の操作席。噴射するセメントの量などを示す計器が並ぶ。
この現場で使用している重機の操作席。噴射するセメントの量などを示す計器が並ぶ。「そこに無事建っている」ということ
施工中も、そして施工完了後も自分の成し遂げた作業の結果が見えない「地盤改良」。酒井さんはどんなところに仕事のやりがいを感じているのだろうか?
「これは、この仕事をしている人間にしかわからないでしょうが…『自分が改良した土地の上に構造物がちゃんと建っている』。それが一番のやりがいですね。『ちゃんと建っている』イコール地盤がしっかりしている、ということですから」
建物や構造物がどれだけ頑丈でも、軟弱な基礎の上には成り立たない。我々が何気なく使っている道路や橋も、酒井さんの、まさに「縁の下の力持ち」とも言うべき仕事に支えられているのだ。
 新潟市内の交通渋滞緩和のため、2022年度の供用開始をめざしている。
新潟市内の交通渋滞緩和のため、2022年度の供用開始をめざしている。 仕事仲間との情報共有、後輩の指導…「意思の疎通は大事です。黙って作業してればいいなんていう時代ではないので」
仕事仲間との情報共有、後輩の指導…「意思の疎通は大事です。黙って作業してればいいなんていう時代ではないので」技能実習生の教育も
日特建設では、日本の先端技術を学びたいという海外からの技能実習生たちの技術習得をサポートする「技能実習制度」を積極的に取り入れ、毎年インドネシアから若いエンジニアを受け入れている。
「技能実習生の指導は、どう教えたらいいのか、毎日試行錯誤ですけれど、彼らは本当に真面目で、純粋に日本の技術を身につけたいと思って来ているので、教えがいがありますよ」
合計3年間、日本で語学と技術を習得することで、母国に帰ってその技術を伝えることができる。日特建設にはインドネシアにグループ会社があるため、そこに就職することも可能だ。
「賛否両論、いろいろな意見がある制度だと思いますが…自分の技術が国際貢献につながることなんてなかなかないことなので」
酒井さんに手ほどきを受けた若い技能者がインドネシアの現場で活躍する日も、そう遠くないだろう。
 インドネシアから受け入れた技能実習生を指導。
インドネシアから受け入れた技能実習生を指導。 来日2年目の技能実習生は、日本語もかなり上達している。
来日2年目の技能実習生は、日本語もかなり上達している。「サカイさんはとても優しいです(笑)」

